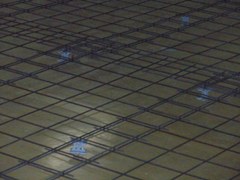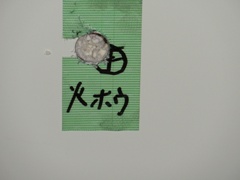2008.12.29(月)
さあ、生コンが投入されました。「投入」と言ったて簡単じゃありません。
表面を平らにして「ほぼ水平」に保つことが必要です。
「ほぼ水平」と言ったのは実は完全な水平では困るのです。床清掃の際に水を流すのに
若干の勾配が必要なのです。
前回、床工事準備の時に説明したように排水溝を作るのですが、排水溝に水が流れる
ように勾配をつけるのです。
 職人さん何人もがコテで
職人さん何人もがコテで
ならしていきます。
この写真には2人しか写っていませんが、
実はもっともっと職人さんがいます。
「ええ、でも固まっていないコンクリート
の上を歩いてだいじょうぶ?」いう声が
聞こえてきますね。大丈夫です。
答えは次の写真を見てください。

この写真のものを靴の下につけて
コンクリートの上にのると沈まないのです。
雪の中を歩く際の「かんじき」ですね。
と言っても実際に履いて歩いた人は
少ないとは思いますが。
上の写真の職人さんの足元をよく
見てください。
この「かんじき」を履いています。
職場、職場には外部の人には知らない「工夫」がいろいろあるものですね。