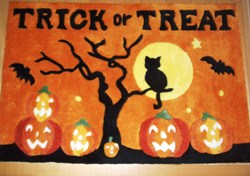未来の野菜を作る 無農薬野菜 AAAレタス 植物工場の採算性
植物工場という「ひとくくり」で、採算性を議論することには無理があります。
同じ業界でも「儲けている」会社もあれば、「儲からない」会社もあります。
経営者の手腕が採算性を左右するということだと思います。
それでも、一般的に言って植物工場を運営する場合には「資金」「運営ノウハウ」「販売」だと
思います。
典型的な「設備産業」である植物工場は、売り上げが伸びてきて、生産能力が足りなくなると
新しい設備を建設するしかないのです。
作業のシフトを増やして(残業)しても、生産量は増えないのです。
このために、「資金」は非常に重要なファクターです。
次は「運営ノウハウ」です。
前回にも説明しましたが、資金があると言って設備を購入しても、運営ノウハウ(ソフト)がないと
品質の良い野菜はできません。
そして最後に「販売」です。
高品質の野菜ができても、販売先がないと売上になりません。(これは当然のことですが)
特に、野菜は「生鮮物」なので販売のタイミングが合わないと無駄になってしまいます。
また、品目ごとに販売が適合しないと「売るものはあるのに」お客さんの「希望する品目が
ない」ということになります。難しいものです。
「資金」「運営ノウハウ」「販売」がうまく連動して採算性が向上するのです。
これはあまりに「当たり前」のことで、何も植物工場に限らないのでしょうが。
植物工場特有のものとしては、「生産規模」についてコメントしたいと思います。
商業規模としては「日産1000株」くらいのものが、小さい工場だと思います。
この規模では「なかなか採算にのせる」のは大変です。
不可能とは言いませんが、利益が出ても大きな利益にはなりません。
筆者の経験とこれまでの数字から判断すると「日産2000~2500株」くらいないと期待する
ような利益はなかなか生まれません。
この規模は採算性を維持する良い規模であり、一方で社員(技術者)ひとりの目が届く規模
ではほぼ限界だと思います。
これ以上大きなものを建設しようと思うなら、「2000~2500株」をひとつのユニットにして
複数ユニットをそれぞれの担当者(技術者)が管理するという手法が良いと思っています。