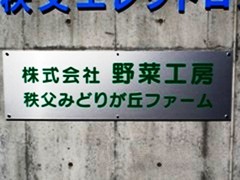2009.02.28(土)
私たちのレタスは「低細菌」を謳っているので「袋」に詰めます。
一般的に言えば「密閉」されていると理解して頂いた結構です。
そのために、袋の口は熱で溶かしてくっ付けてしまいます。
私たちの事前サンプルは針金で留めたものもありましたが、実際の商品は「ヒートシーラー」と
いう機械で溶かしてくっ付けるのです。

これがヒートシーラー
ですね。
私たちのは手動式で
かわいいおもちゃみたい
なものです。
将来的に生産量が多くなって、手動式では追いつかないようになったら自動連続式のものに
することになるのでしょうが、現在は「心を込めて」「ひとつひとつ」シールをしていきます。