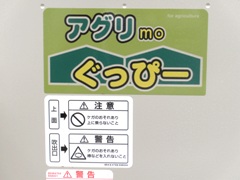2010.07.14(水)
未来の野菜を作る 無農薬野菜 AAAレタス 変電設備と冷蔵庫
前回に続いて建物の外にある設備をご紹介します。
「変電設備」と「冷蔵庫」です。
私たちの栽培設備は「完全閉鎖型噴霧水耕栽培」です。
太陽光を使わない代わりに「蛍光灯」の光をレタスにあてます。
また、気温をコントロールするために「エアコン」を使います。
そのために電気を使っていますが、多くの工場でも同じようにいわゆる「高圧電力」を東京電力から
購入して「変圧」(100ボルトや200ボルト)して使用しています。
その変圧するための設備が変電設備です。通常は「キュービクル」と呼ばれています。

これが
キュービクルです
こんな設備を
いろいろなところで
見たことが
あるでしょう?

一部をアップすると
「変電設備」
「高圧受電盤」という
表示があります
このキュービクルはちょっと大きな施設には良くあります。
筆者が良く行く市営プールにも駐車場の隅にあります。注意してみるといろいろな所にありますよ。
もうひとつの設備は「冷蔵庫」です。
収穫したレタスを「仮保管」するためのものなので小さなものですが。

クール宅急便が取りに
車での間などに
保管します
建物の外にもいろいろな設備があるということをご説明しました。